 
■ 「涅槃の道場 (香川県)」 ■ |
■5月24日(木)天候 曇り■ 自転車 Odo 1181.3-1241.3km (走行キロ60.0km)
4時に起床。
夜中に何度も、道の駅で飼われているペアの孔雀に「カァー」の鳴き声で目覚めたが、それほど辛くはない。
身支度をして荷物を整え、久しぶりにブラックコーヒーを飲む。
豆の香りがいい!
|
| 5時30分 |  この後すぐ241号線の分岐点 この後すぐ241号線の分岐点 |
 海岸線とも暫くお別れ… 海岸線とも暫くお別れ… |
|
8号線との交差点は地図通り横切り、暫く行くと喫茶「萩」があり、ここで右折、雲辺山ロープウェイ乗り場に向かう。 喫茶「萩」を過ぎて登り坂になり、点在する農家や住宅を通り過ぎ、途中から一方通行路になります。 交通事故を避けるため地元の配慮が隠されています。 残り3kmぐらいから急登になり、ここから歩き自転車遍路に変身。 今日は身体の調子が良いようです。 水分補給し筋肉を労わりながら登りの距離が続く。 |
 ここは一方通行路です ここは一方通行路です |
 一方通行が終わり残り1kmの標識 一方通行が終わり残り1kmの標識 |
 雲辺寺ロープウェイ乗り場 雲辺寺ロープウェイ乗り場 |
←7時5分
|
|
一緒に行くことになり、料金が2000円は高いと係員にブッブッ言っていたが、
自転車の私にとっては、時間と体力の消耗を考えたら安いくらいで妥当と云える。
四国の自動車遍路は、小さい車両の方が便利だと話して、逆打ちで遍路していると教えてくれた。
|
 最初に従業員が上の駅へ… 最初に従業員が上の駅へ… |
 空中散歩気分で撮影 空中散歩気分で撮影 | | |
 | | 陰影の濃淡が私のお気に入り 陰影の濃淡が私のお気に入り |
|
■ 編集メモ ----------------------------------------------------------------------------------------- |
|
…自転車を頂上駅舎に置いて、標高880mの雲辺寺までは坂を下る。 境内に続く下り坂道に比較的新しい五百羅漢が出迎えてくれる。 境内は全体が修復している途中の様で、歩くコースも、堂宇の石段も新しく白いです。 寝釈迦、本堂、仁王門も新築で、仁王門は最近建立されたようで、古くからある歩き遍路の人がくる道の仁王門は、取り壊されて今はありません。 これだけ境内の中が新しいものが多いと、いまひとつ感動が少ない。 これも年月を重ねれば味わい深くなるのではないか。 |
-----------------------------------------------  ■第66番札所 巨鼇山 千手院 雲辺寺■
■第66番札所 巨鼇山 千手院 雲辺寺■宗 派: 真言宗御室派 本 尊: 千手観世音菩薩(経尋作) 開 基: 弘法大師 創 建: 延暦8年(789年) 真 言: おん ばざらたらま きりく 御詠歌: はるばると雲のほとりの寺に来て 月日を今は麓にぞ見る ★彡 第66番札所 雲辺寺の拡大映像 |
第66番札所 巨鼇山 千手院 雲辺寺 7時33分 |
 駅舎から左方向へ下る 駅舎から左方向へ下る |
 寝釈迦 寝釈迦 |
|
鎌倉時代には多くの堂宇を構え、四国各地から修行僧が集まり、学問を修める場として大いに栄え、四国高野とも云われた。 その傾斜のある広い境内に、新旧堂宇が点在し、古い堂宇には古刹を感じる。 戦国時代に堂塔は焼失し荒廃したが、その後、阿波藩主蜂須賀家に保護を受け再建された。 |
 五百羅漢の説明板 五百羅漢の説明板 手水舎 手水舎 仁王門をくぐって石段を上る 仁王門をくぐって石段を上る 本堂 本堂 大師堂 大師堂 |
 | | 仁王門 仁王門 鐘楼 鐘楼 現在の本堂ができるまで仮本堂だった 現在の本堂ができるまで仮本堂だった 護摩堂 護摩堂 |
|
境内に五百羅漢の説明板があり、ここに引用します。 |
| 五百羅漢 |  |
 |
|
8時に頂上駅に戻るとロープウェイは20分ごとの発車で、タイミング良く下に降りる時刻だった。
習志野の人が待っていてくれた。
一緒に乗車して、下の駐車場に到着した。
|
 |
|
今日は5月24日、5月6日から髭は剃ってないし、退職して髪を染めるのをやめた。
顔全体が白髪ぼうぼうのお爺さんだから、見た目にはベテランの遍路に見えるかも…。
|
| 8時20分 |  誰にも遭わずに… 誰にも遭わずに… |
 この分岐点を過ぎて確か民宿があるはず… この分岐点を過ぎて確か民宿があるはず… |
|
岩鍋池の先を右折して、大寶寺の裏側から回り込むはずだったが、この後、現在地が判らなくなった。
点在する民家付近で道が判らなくなり、庭掃除していたお爺ちゃんに尋ねた。
|
 少し安心… 少し安心… |
 岩鍋池の先で現在地が判らなくなった 岩鍋池の先で現在地が判らなくなった |
|
大寶寺の裏側から回り込んで、
駐車場は2台の自家用車があるだけで、殺風景の感じがして自転車の置き場所を仁王門の横に置こうと移動していたら、
バスが反対の道からこちらに向かってきた。
私の来た方向と違うので地図で確認すると68番神恵院から来たようで、どうやら逆打ち遍路バスの団体でした。
  ■第67番札所 小松尾山 不動光院 大興寺■
■第67番札所 小松尾山 不動光院 大興寺■宗 派: 真言宗善通寺派 本 尊: 薬師如来(伝弘法大師作) 開 基: 弘法大師 創 建: 天平14年(742年) 真 言: おん ころころ せんだり まとうぎ そわか 御詠歌: 植ゑ置きし小松尾寺を眺むれば 法の教への風ぞ吹きぬる ★彡 第67番札所 大興寺の拡大映像 |
|
田圃の中に広がる大寶寺は仁王門から鬱蒼とした森を背景にしてあった。 仁王門の暖簾の様な白布が美しい。仁王門の横に自転車をスタンドで止めた。門に寄せて傷がついたら大変。 バスから降りてきた逆打ちの団体さんと一緒に92段の長い石段を登ると明るい境内になり、落ち着いた雰囲気のあるお寺でした。 |
第67番札所小松尾山 不動光院 大興寺 8時55分 |
 大きな仁王門 大きな仁王門 |
 | | |
|
… 遍路準備一言 --------------------------------------------------------------------------------------
|
 鐘楼 鐘楼 |
 本堂 本堂 |
|
大興寺は真言宗と天台宗両方の修行道場として珍しい歴史がある。 このため本堂に向かって左側の弘法大師堂とともに、右側に天台宗第三祖智顗を祀る天台大師堂があった。 団体の添乗員の説明を横で聞いていて勉強になった。そして本堂内に納経所があった。 |
 本堂の左側にある弘法大師堂 本堂の左側にある弘法大師堂 寺坊 寺坊 |
 本堂の右側にある天台大師堂 本堂の右側にある天台大師堂 68番神恵院、69番観音寺の標識 |
 朽ちた土塀 朽ちた土塀 |
-------------------------------------------------
|
|
標識を発見して観音寺市内を通過すると財田川を渡って、68番神恵院、69番観音寺に到着。
…ここには琴弾八幡宮があり、琴弾公園として観光地として有名だ。
|
 老夫婦に撮影してもらう 老夫婦に撮影してもらう |
|
老夫婦は柔和な笑顔で、「道中、後半だが無事で結願を…」と言い、軽自動車に乗って行った。(感謝!)
  ■第68番札所 七宝山 神恵院■
■第68番札所 七宝山 神恵院■宗 派: 真言宗大覚寺派 本 尊: 阿弥陀如来 開 基: 日証上人 創 建: 大宝3年(703年) 真 言: おん あみりた ていぜい からうん 御詠歌: 笛の音も松吹く風も琴弾くも 歌うも舞うも法の声々 ★彡 第68番札所 神恵院の拡大映像 |
-----------------------------------------------  ■第69番札所 七宝山 観音寺■
■第69番札所 七宝山 観音寺■宗 派: 真言宗大覚寺派 本 尊: 聖観音世音菩薩 開 基: 日証上人 創 建: 大宝3年(703年) 真 言: おん あろりきゃ そわか 御詠歌: 観音の大悲の力強ければ おもき罪をも引きあげてたべ ★彡 第69番札所 観音寺の拡大映像 |
| 10時13分 |  仁王門 仁王門 鐘楼 鐘楼 |
 | | 鐘楼 鐘楼 |
| 第68番札所神恵院へ |  神恵院 本堂入口をくぐると… 神恵院 本堂入口をくぐると… |
 神恵院 本堂 神恵院 本堂 |
 神恵院 大師堂 神恵院 大師堂 |
------------- 余談 ---------------- |
| 第69番札所観音寺へ |  観音寺 本堂(国重文) 観音寺 本堂(国重文) |
途中で両替をしようとしても、その機会に恵まれない時がある。
|
|
観音寺の本堂は、室町時代初期の建立で、国指定重要文化財です。 本堂、大師堂とも一重の本瓦屋根で、それほど大きくないが、朱塗りの柱が印象的で、堂々した気品が感じられる。 それぞれの本堂と大師堂で、納経し、納経所で一括して、納経帳に筆入れして貰いました。 |
 観音寺の大師堂は石段を… 観音寺の大師堂は石段を… |
 観音寺 大師堂 観音寺 大師堂 |
|
隣に道の駅ことひきがあり、目の前は瀬戸内海です。 境内をさらに登って行くと、琴弾八幡宮があり、その途中、海の方に向かうと銭形展望台があり、ここから寛永通宝の砂絵がみえる。 さらに、根上り松など観光には事欠かないし、近くには金刀比羅宮も近い。 この付近だけで、一日二日は観光ができる処が盛りだくさんあります。 行きたい気持ちと遍路中! 葛藤があったが遍路を優先しました。 |
 納経所 納経所 |
 | | |
|
ここから70番本山寺まで5kmの道のりを走ります。
財田川に沿って川上へ一本道、車両の通らない土手沿いをのんびりとペダルをこぎながら走り、JR予讃線をくぐると左手に五重塔が見えてきます。
5月も終わりに近づき、土手沿いには背の高い葦や、小さな花の群性を見る事ができる。
こんな気持ちになるのは何故だろう!
  ■第70番札所 七宝山 持宝院 本山寺■
■第70番札所 七宝山 持宝院 本山寺■宗 派: 高野山真言宗 本 尊: 馬頭観音 開 基: 弘法大師 創 建: 大同2年(807年) 真 言: おん あみりとう どはんば うん ぱった そわか 御詠歌: もとやまに誰か植江ける花なれや 春こそたをれたむけにぞなる ★彡 第70番札所 本山寺の拡大映像 |
第70番札所 七宝山 持宝院 本山寺 11時20分 |
 仁王門(国重文) 仁王門(国重文) 鐘楼 鐘楼 本堂(国宝) 本堂(国宝) 十王堂と奥殿の護摩堂 十王堂と奥殿の護摩堂 |
 広い境内 広い境内 阿弥陀堂 阿弥陀堂 大師堂 大師堂 納経所 納経所 |
|
本山寺の文化財を気に入って納経後も暫く境内を散策する。 特に、本堂は国宝で良い映像が欲しいから、人が途切れるまで待って撮影。 そして広い境内を移動して、いろいろな角度から堂宇を眺めているだけで、自分が今、遍路修行している事を自覚する。 とても気持ちが充実する。 |
 五重塔 五重塔 |
納経して、すぐ次のお寺へ向かうのもいいが、その逆に、ここにいると何か再発見できるかもしれない…。
 |
 | | |
 12時30分 |
|
71番弥谷寺に向かって11kmの距離を走る。
国道11号線にでて、高松自動車道の手前を左折、両側に溜池のある深尾を右折して、弥谷寺の標識を見つける。
ここから急登な登り坂が待っていた。
「ありゃ~!」見ただけで圧倒される急坂である。
初めから自転車を押して歩きだした。(降参!)
|
-----------------------------------------------  ■第71番札所 剣五山 千手院 弥谷寺■
■第71番札所 剣五山 千手院 弥谷寺■宗 派: 真言宗善通寺派 本 尊: 千手観世音菩薩 開 基: 行基菩薩 創 建: 天平年間(729年~749年) 真 言: おん ばざら たらま きりく 御詠歌: あくにんとゆきつれなんも弥谷寺 ただかりそめも良きともぞよき ★彡 第71番札所 弥谷寺の拡大映像 |
|
弥谷寺へ向かう道の横に、弥谷寺第二駐車場があったが、バス用で車の姿はない。 車には出逢うが人は見かけなかった! どこかに自転車を置かなければと思いつつ、自転車を押して歩く。 丁度、カーブの曲がり口で、飲料メーカーや自家用車がある小さな駐車場で、自転車の置き場所を見つけた。 |
第71番札所 剣五山 千手院 弥谷寺 13時5分 |
 自転車を置いてここからスタート… 自転車を置いてここからスタート… |
 | | |
| 駐車場から、ここからは長~い、長~い石段が果てしなく続きます。 仁王門から長い石段を上ると堂宇が岩山に点在している。 岩盤から突き出たような堂宇を見て山岳霊場を感じさせる雰囲気です。 |
 仁王門 仁王門 |
 | | |
| 弥谷山は昔から霊山として信仰されたと云われ、人々は山に仏や神が宿ると信じ、霊山として山岳霊場信仰の対象としたとされています。 木々が茂るこの時期はより一層その雰囲気が漂っていました。 |
 | | | | 本堂まであと170段の石段が… 本堂まであと170段の石段が… |
 参道途中にある菩薩像 参道途中にある菩薩像 寺坊 寺坊 | | |
|
各堂宇まで石段が続き、本堂はさらに石段が続きました。
ぐる~っと、一回りするまで石段が続き、自分でつけた名前が「石段は弥谷ー(いやだにー)」。(…大師様、ごめんなさい!) |
 紅葉の時期に来てもいいかも! 紅葉の時期に来てもいいかも!   | | 本堂 本堂 |
 岩窟に造られた護摩堂 岩窟に造られた護摩堂   岸壁に彫られた磨崖仏の阿弥陀三尊像 岸壁に彫られた磨崖仏の阿弥陀三尊像 一番上の本堂前からの景観 一番上の本堂前からの景観 |
| 大師堂へは靴を脱いでお堂内に入ります。木の温もりを感じる堂内は神聖な雰囲気がある。 大師堂内に納経所があり、読経、納経後に堂内を撮影したが、ほとんどが掲載できない映像で、自分でも呆れてしまった。 |
 大師堂と納経所 大師堂と納経所 左手に納経所、右手に大師堂 左手に納経所、右手に大師堂 |
 | | ピンボケ映像 ピンボケ映像 |
 |
…14時3分
|
四国の瀬戸内海側は農業灌漑用の溜池が非常に多い。 曼荼羅寺に着いて、お茶屋の店先に自転車を置かせてもらった。 ここならば第73番の出釈迦寺も歩いて行ける。 -----------------------------------------------   ■第72番札所 我拝師山 延命院 曼荼羅寺■
■第72番札所 我拝師山 延命院 曼荼羅寺■宗 派: 真言宗善通寺派 本 尊: 大日如来 開 基: 弘法大師 創 建: 大同2年(807年) 真 言: おん あびらうんけん ばざらだどばん 御詠歌: わずかにも曼荼羅拝む人はただ 再び三度帰らざらまし ★彡 第72番札所 曼荼羅寺の拡大映像 |
| 創建は四国霊場で最も古い推古4年(596年)といわれ、その後、弘法大師が訪れ亡き母の冥福を祈るため堂宇を建立した。 本尊に大日如来を祀り、唐から持ち帰った曼荼羅を安置し、寺名を曼荼羅寺にした。 |
第72番札所我拝師山 延命院 曼荼羅寺 14時19分 |
 仁王門 仁王門 | | |
 | | 新しい石像が多い 新しい石像が多い |
|
曼荼羅寺仁王門をくぐり、先ず、手水舎に寄り、鐘を撞きにゆくと、鐘は鐘楼の中に入って撞いて下さい。と張り紙があった。 新しく造られた大日如来像や福禄寿、修行大師像、青銅製の延命地蔵が境内に並んでいる。 不老松は不老長寿笠松大師として甦りました。と案内があった。 |
 本堂 本堂 大師堂 大師堂 |
 鐘楼 鐘楼 護摩堂 護摩堂 |
|
曼荼羅寺から出釈迦寺まで、約500mぐらい登り坂を行きます。
大型バスの団体グループは、二手に分かれて参拝するようで、一緒に坂を登った。
賑やかなお喋りを聞きながら、香川県の霊場は結構移動距離が短い。
|
 観音堂 観音堂 |
|
涅槃の道場に入って何か余裕が無くなった気がする。 札所間が短くなり考える時間が無くなった。自分で調節した方がいいんじゃないかと思った。 -----------------------------------------------  ■第73番札所 我拝師山 求聞持院 出釈迦寺■
■第73番札所 我拝師山 求聞持院 出釈迦寺■宗 派: 真言宗御室派 本 尊: 釈迦如来 開 基: 弘法大師 創 建: 奈良時代後期~平安時代前期 真 言: のうまく さんまんだ ぼだなん ばく 御詠歌: 迷いぬる六道衆生救わん 尊き山に出づる釈迦寺 ★彡 第73番札所 出釈迦寺の拡大映像 |
|
出釈迦寺の開基には、弘法大師の幼少期の伝説の一つ、捨身ヶ嶽に所縁があります。 出釈迦寺から約1時間、標高481mの我拝師山の断崖から身を投げた場所が、捨身ヶ嶽禅定と伝わります。 団体の遍路と一緒だと、先達の人が話すお寺の縁起も聞こえてくるから勉強になります。 |
第73番札所我拝師山 求聞持院 出釈迦寺 14時41分 |
 出釈迦寺入口 出釈迦寺入口 | | |
 修行大師像と後背に我拝師山 修行大師像と後背に我拝師山 山門 山門 |
|
■灯明をあげて ------------------------------------------------------------------------------- |
 本堂 本堂 |
 大師堂 大師堂 |
|
曼荼羅寺を打ち、歩いて出釈迦寺と両方打ってきた。
駐車場に戻ると、おじさんが冷たいお茶を出してくれた。
今日は何処に泊まるのかと聞かれたが、善通寺市内の民宿をあたると話す。
団体の大型バスが3台も到着して、曼荼羅寺、出釈迦寺の付近は賑やかで、お茶屋のおじさんも忙しそうに戻った。
|
 筆の山(出釈迦寺と曼荼羅寺の途中で見える) 筆の山(出釈迦寺と曼荼羅寺の途中で見える) |
-----------------------------------------------  ■第74番札所 医王山 多宝院 甲山寺■
■第74番札所 医王山 多宝院 甲山寺■宗 派: 真言宗善通寺派 本 尊: 薬師如来(伝弘法大師作) 開 基: 弘法大師 創 建: 平安時代初期 真 言: おん ころころ せんだり まとうぎ そわか 御詠歌: 十二神味方に持てる戦には 己と心かぶと山かな ★彡 第74番札所 甲山寺の拡大映像 |
第74番札所 医王山 多宝院 甲山寺 15時15分 |
 山門 山門 |
 左手に鐘楼 左手に鐘楼 |
|
境内奥に、古刹を感じる毘沙門天の岩窟がありました。 お寺周辺は弘法大師の故郷で、幼少時代によく遊んだといわれる場所だそうです。 京に暮らしていた弘法大師が溜池の造営のため故郷の讃岐に戻った時、甲山寺に工事の無事を祈願して薬師如来像を安置したという。 |
 中門 中門 毘沙門天の岩窟 毘沙門天の岩窟 |
 本堂 本堂 大師堂 大師堂 |
|
75番善通寺は甲山寺を出て県道に出ると、遠くからでも五重塔が見えて目印になった。 駐車場で管理人が自転車の置き場所を指定した。これなら安心。 善通寺は御影堂(西院)と善通寺本堂(東院)に分かれ、その間を道路が通り、境内が広すぎて暫くウロウロして手間取った。 結局、駐車場から入って、西院から中門を通り、東院で境内全体を把握してから、南大門から入ることにした。 -----------------------------------------------  ■第75番札所 五岳山 誕生院 善通寺■
■第75番札所 五岳山 誕生院 善通寺■宗 派: 真言宗善通寺派 本 尊: 薬師如来 開 基: 弘法大師 創 建: 大同2年(807年) 真 言: おん ころころ せんだり まとうぎ そわか 御詠歌: 我すまばよもきゑはてじ善通寺 ふかきちかいの法のともしび ★彡 第75番札所 善通寺の拡大映像 |
第75番札所 五岳山 誕生院 善通寺 15時45分 |
 駐車場エリア 駐車場エリア |
 済世橋 済世橋 |
| 駐車場から境内に向かいます。 入口には済世橋と呼ばれる西院に架かる橋があり、中国風の橋とその先に正覚門も中国風で、昭和54年に建立された。 |
| 西院 誕生院へ |  太鼓型石橋の済世橋 太鼓型石橋の済世橋 済世橋上の景観 済世橋上の景観 |
 正覚門 正覚門 西院へ 西院へ |
 パコダ供養塔 |
 遍照閣…研修道場 遍照閣…研修道場
西院には、中央に御影堂が配され、周囲にパコダ供養塔、研修道場の遍照閣、聖天堂、光明殿、戦没英霊堂の聖霊殿、護摩堂(不動明王)、 そして鐘楼、納経所がある。 |
|
 聖天堂 聖天堂 |
 光明殿 光明殿 |
| 御影堂(大師堂)は弘法大師誕生の邸宅があった場所に、天保2年(1831年)に建立され、昭和11年に修復された。 |
 御影堂(右側面) 御影堂(右側面) 御影堂への回廊 御影堂への回廊 護摩堂…不動明王 護摩堂…不動明王 御影堂(大師堂) 御影堂(大師堂) |
 聖霊殿…戦没英霊堂(後方から) 聖霊殿…戦没英霊堂(後方から) 鐘楼 奥に納経所 鐘楼 奥に納経所 聖霊殿…戦没英霊堂 聖霊殿…戦没英霊堂 西院仁王門から撮影、回廊、そして御影堂 西院仁王門から撮影、回廊、そして御影堂 |
|
御影堂と善通寺本堂の間に道路が通り、それぞれ四方に門があるので山門を探すのに手間取った。 一旦、善通寺を出て、改めて南大門から入ります。 南大門は善通寺の正門で、街の商店街に続いてるので賑やかでした。 永禄元年(1558年)の戦によって、創建当時からの堂宇すべてが、全焼したのは大変残念に思います。 |
 西院の仁王門、石橋は廿日橋 西院の仁王門、石橋は廿日橋 観智院 観智院 |
 東院へ続く石畳 東院へ続く石畳 東院の中門 東院の中門 |
|
尚、2012年12月に金堂(本堂)と五重塔が国登録有形文化財から国指定重要文化財に格上げされました。
まだ多くの国登録有形文化財があるから、将来、重要文化財になり、日本の宝が増える。 |
| 15時54分 五重塔(国重文) |
 広い境内 広い境内 | | |
 | | 鐘楼堂 鐘楼堂 |
|
|
 南大門…善通寺の正門 南大門…善通寺の正門 常行堂(釈迦堂) 常行堂(釈迦堂) |
 金堂(本堂)(国重文) 金堂(本堂)(国重文) 樹齢1000年を越える大楠 樹齢1000年を越える大楠 |
|
納経が終わったのが16時45分でした。 この時間帯は人が少なく閑静で、多くのお堂をじっくり見学できた。 五重塔も素晴らしい建物で印象深かった。 |

自分の映像を見て、左肩が下がっているのでがっくりした! 現在は直立不動の姿勢だが、遍路中は姿勢が偏っていたことに驚いた。 納経が終わって見回していると、見ていたお寺の人が記念撮影に協力してくれた。(感謝!) |
 |
|
 東院中門から再び、西院誕生院へ 東院中門から再び、西院誕生院へ |
 再び廿日橋を渡って西院の仁王門へ 再び廿日橋を渡って西院の仁王門へ |
|
さすがに大師さんの誕生の地です。 高野山、京都の東寺と共に大師三大霊場のひとつだけある。 南大門には門前にお土産店や遍路洋品店、食事処が並んでいて善通寺駅も近いから大変な賑わいです。 短時間の中で西院、東院とそれぞれの堂宇を回ってきたが、もう一度ゆっくりと来てみたい。 最後に、御影堂本堂内で読経し、駐車場に戻った。 |
| 16時45分 |  西院の仁王門、回廊、御影堂 西院の仁王門、回廊、御影堂 |
 御影堂内に… 御影堂内に… |
|
今日はここまで…。
境内には清掃関係の人しか見なくなり、17時20分に駐車場を出て宿探し、
遍路地図にある善通寺グランドホテルに行き、フロントで素泊り4800円と聞き今夜の宿とした。
|
||
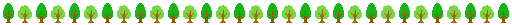 |