 
■ 紀伊山地高野山霊場と参詣道 ■ |
■…高野山奥之院(世界遺産)の供養塔 …■ |
 | | |
 この先、左手に大供養塔がある この先、左手に大供養塔がある |
|
長い歴史の中、供養のため石塔を背負い高野山に登った多くの人々の願いがある。 多くは五輪搭の形をしているが、その小ささに後世の人々がよだれ掛けをかけたものも多くあり、お地蔵さんと思われている石塔も数多くある。 |
 | | |
 玉川橋 玉川橋 |
|
歴史に名を残した人も、無名の人も、ここでは同じように安らぐ魂として存在しているのではないか。 高野山はそのすべてを受け入れている。 玉川橋を渡った所で、この道は中の橋駐車場に向かうと観光グループの案内に教えて貰い、もと来た道に戻る。 金剛三昧院の人から月曜日は観光客が少ないと云われたが参詣者は昨日より少ない。 持参した資料を見ながら一の橋まで歴史散歩。 |
 | | 浅野内匠頭と赤穂四十七士供養塔 浅野内匠頭と赤穂四十七士供養塔 |
 奥の院の参詣道に戻る 奥の院の参詣道に戻る | | |
|
奥の院参詣道の中の橋付近から覚鑁堂までの間が坂道となっていて、この坂を「かくばん坂」と呼ばれている。 この坂で転ぶと寿命が3年以内であるという伝説もある。 参道を歩き始めて、時間に追われ歴史上の人物の供養塔を見るだけに気をとらわれていると 何か大切なものを見逃すことがあるんではないかと思った。 心を空白にして奥の院の空気の中に身を置き、何かを感じようと気を引き締めた。 |
 肥前島原 松平家供養塔 肥前島原 松平家供養塔 |
 なだらかな坂(かくばん坂) なだらかな坂(かくばん坂) |
|
空海が構想した高野山、寺院そのものが密教構想によってつくられたということはインドや唐にも存在しないことだった。 これは空海が師恵果から伝法阿闍梨位の灌頂をうけ、真言密教第八祖として密教の体系を最終的に純化させたことを意味する。 そして知られていないのが日本の書の開祖といわれている。 日常、書いてきた文字の形が、1200年前から始まったことを知り得たことは大きな収穫です。 |
 なだらかな坂(かくばん坂) なだらかな坂(かくばん坂) | | |
 | | 安芸 浅野家供養塔 安芸 浅野家供養塔 |
|
汗かき地蔵堂… |
 汗かき地蔵堂 汗かき地蔵堂 中の橋 中の橋 |
 姿見の井戸 姿見の井戸 伊勢桑名城主 本多忠勝供養塔 伊勢桑名城主 本多忠勝供養塔 |
|
中の橋… |
 明智光秀供養塔 明智光秀供養塔 島津初代家久、二代光久、綱久供養塔 島津初代家久、二代光久、綱久供養塔 伊達正宗供養塔 伊達正宗供養塔 周防岩国 吉川家供養塔 周防岩国 吉川家供養塔 |
 石田三成供養塔 石田三成供養塔 母子像 母子像 周防岩国 吉川家供養塔 周防岩国 吉川家供養塔 紀州徳川家(光貞、綱教、宗直)供養塔 紀州徳川家(光貞、綱教、宗直)供養塔 |
|
供養塔の中で鳥居のあるものが多いが、際立つのは徳川家の供養塔で鳥居の入口に石扉が多い。 そして武田信玄公の供養塔の前に腰掛け石がある。 昔は息処石と書いて腰掛け石と読んだそうです。 弘法大師が休憩で腰を掛けた石であるという云い伝えがある。 腰掛け石は六角形の石枠で保護され、隣に石碑がある。 |
 弘法大師の腰かけ石 弘法大師の腰かけ石 武田信玄 勝頼供養塔 武田信玄 勝頼供養塔 |
 腰掛け石を上から覗いた 腰掛け石を上から覗いた 紀州徳川家 七代宗将供養塔 紀州徳川家 七代宗将供養塔 |
|
参詣道は大木に囲まれ陽光が入り、苔むした石塔や山内地特有の蚊が多く、私の身体は大分美味しいようで蚊に散々食われた。 防虫スプレーを車に残したのを後悔した。 石畳道から外れて山内地の奥へ登る小道があり、そこにも多くの供養塔があるが、今回は準備不足だった! |
 紀州初代藩主 徳川順宣供養塔 紀州初代藩主 徳川順宣供養塔 | | |
 高野山町石道 高野山町石道 山口毛利家供養塔 山口毛利家供養塔 |
|
…司馬遼太郎文学碑 ------------------------------------------------------------------------ |
 司馬遼太郎文学碑 司馬遼太郎文学碑 |
 石畳道が広くなりもうすぐ一の橋です 石畳道が広くなりもうすぐ一の橋です |
|
司馬遼太郎の作品「空海の風景」がNHKスペシャル「空海の風景」で2002年1月に放送されました。 |
 | | |
 奥州仙台伊達家供養塔 奥州仙台伊達家供養塔 |
|
海軍第十四期飛行予備学生戦没者慰霊塔 ああ同期の桜… |
 一の橋上から見る御殿川 一の橋上から見る御殿川 |
 海軍第十四期飛行予備学生戦没者慰霊塔 海軍第十四期飛行予備学生戦没者慰霊塔 |
|
奥の院一の橋… |
 奥の院一の橋 奥の院一の橋 |
 高野山町石道 高野山町石道 |
|
奥の院の歴訪で一の橋まで来て、一の橋観光案内所で休憩。 ここの駐車場は有料です。 喫煙して冷たい飲料で大休憩した。 妻も歩き疲れたのかタイミング良い休憩となった。 日陰のベンチで腰かけると爽やかな風が吹き抜けていく。 暫く休んでから再び一の橋から参詣道に向かう。 参詣道が二手に分かれていたのでもう一方を見学し、見落とした処もあるかもしれないので参詣道を通って中の橋駐車場に戻る予定。 |
 もう一方の参詣道 もう一方の参詣道 |
 関東大震災供養塔 関東大震災供養塔 |
|
五族の墓… |
 五族の墓 五族の墓 |
 六地蔵尊灯籠塔 六地蔵尊灯籠塔 |
|
五族の墓を通り、その石畳の先に六地蔵尊灯籠塔という建物がある。 灯籠塔の建設発起人は野村晃円という尼僧で、弘法大師の夢告げを受けて発願したという。 尼僧は全国を行脚、寄進を募って建設費用を調達し、完成は昭和39年で高野山が開かれて1150年、さらに明治から数えて100年を記念しての建物となった。 |
 信州松本 水野家供養塔 信州松本 水野家供養塔 |
 源氏の祖 多田満仲供養塔 源氏の祖 多田満仲供養塔 |
|
源氏の祖 多田満仲供養塔… |
 奥州南部家供養塔 奥州南部家供養塔 上州館林 榊原康政供養塔 上州館林 榊原康政供養塔 |
 上杉謙信廟(世界遺産)…清浄心院 上杉謙信廟(世界遺産)…清浄心院 阿波徳島 蜂須賀家供養塔 阿波徳島 蜂須賀家供養塔 |
|
密厳堂… |
 | | 密厳堂 真言宗中興の祖 密厳堂 真言宗中興の祖 |
 密厳堂入口 密厳堂入口 高麗陣敵味方戦死者供養碑 高麗陣敵味方戦死者供養碑 |
|
☆彡 一の橋、中の橋、上杉謙信廟、密厳堂、汗かき地蔵堂と姿見の井戸、御廟橋と燈籠堂 の拡大映像
|
 豊後岡 中川家供養塔 豊後岡 中川家供養塔 |
 奥之院参道ガイドマップ 奥之院参道ガイドマップ |
 五輪塔の説明 |
 五輪塔は主に供養塔、墓塔として使われる仏塔の一種で五輪卒塔婆、五輪解脱とも呼ばれる。 五輪塔の形はインドが発祥といわれ、本来舎利(遺骨)を入れる容器として使われていたといわれるが、 日本では平安時代末期から供養塔、供養墓として多く使われるようになる。 |
|
中の橋駐車場に戻り、時間もお昼近くになり、近くのレストランへ昼食に向かう。
今日の予定はあと清浄心院と金剛三昧院を予定。
昨日に比べて時間的にはのんびり見学できる。 |
||
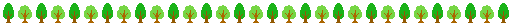 |