 
■ 紀伊山地高野山霊場と参詣道 ■ |
■ 高野山奥之院(世界遺産)へ満願成就 ■ |
 | | 中の橋駐車場前 中の橋駐車場前 |
 観光バスのガイドに頼んで… 観光バスのガイドに頼んで… 奥の院入口(中の橋駐車場前) 奥の院入口(中の橋駐車場前) |
|
昨日の混雑を考えて早めに出発しようと準備していたら、お寺の人に「今日は月曜日だから朝はゆっくりして出掛けて下さい」と言われた。 門前にはバスが止まり観光客が少しずつ集まっている。 境内で記念撮影や堂宇の撮影に賑やかです。 8時を回って金剛三昧院を出発。 車を中の橋駐車場に入れて奥の院に向かう。 |
 南無大師遍照金剛の石柱塔 南無大師遍照金剛の石柱塔 奥の院授受所 奥の院授受所 新明和工業の供養塔はロケットの形 新明和工業の供養塔はロケットの形 |
 手水舎でお浄め 手水舎でお浄め 広い石畳道 広い石畳道 しろあり供養塔 しろあり供養塔 |
|
遍路姿に着替えて奥の院に入り、最初の手水舎でお浄めをする。 「さぁ、行こう」としたら私達より年配のご夫婦が「遍路のお礼参りですか」と聞かれ、自転車遍路の話で長引いてしまった。 ご夫婦は度々お参りに来ると話され、私達の記念撮影をしてくれた。 |
 救世観音像 救世観音像 親鸞聖人の供養塔入口案内 親鸞聖人の供養塔入口案内 見真大師像(浄土真宗開祖親鸞)  徳川家の葵の御紋の宝塔 徳川家の葵の御紋の宝塔 |
 親鸞聖人の供養塔入口案内 親鸞聖人の供養塔入口案内 浄土真宗の宗祖、親鸞聖人の供養塔 浄土真宗の宗祖、親鸞聖人の供養塔
 金剛三昧院の動物供養塔 金剛三昧院の動物供養塔 |
|
広い境内には、皇室、公家、大名、戦国武将などの供養塔から企業、庶民、生き物に至るまで、
あらゆる階層の人々が宗派をこえて供養塔が多数見る事ができる。
排他性の強い宗教で、ここまでオープンにしている処は高野山しかないと感じた。
|
 | | | | 奥殿 奥殿 東日本大震災供養塔建立予定地 東日本大震災供養塔建立予定地 |
 紅葉の時期には… 紅葉の時期には… 英霊殿 英霊殿 阪神淡路大震災物故者慰霊碑 阪神淡路大震災物故者慰霊碑 | | |
|
英霊殿のそばに阪神淡路大震災物故者慰霊碑を発見。 また東日本大震災供養塔建立予定地もある。 ここから参道は鬱蒼とした林の中に入って行く。 突き当たると一の橋から来る道とここで合流する。 聖なる地、聖地と呼ばれる高野山の中でも、弘法大師の御廟のある奥の院は、特に尊い場所であると昔から信じられてきた。 |
 | | |
 奥の院へ向かう 奥の院へ向かう |
|
|
 伊予松山松平家供養塔 伊予松山松平家供養塔 加賀前田利長夫人供養塔 加賀前田利長夫人供養塔 安芸浅野家供養塔 安芸浅野家供養塔 |
 加賀前田利長供養塔 加賀前田利長供養塔 浄土宗の開宗 法然上人圓光大師供養塔 浄土宗の開宗 法然上人圓光大師供養塔 結城秀康石廟 結城秀康石廟 |
|
奥の院の石碑はよくお墓と呼ばれているが、埋葬するお墓ではなく、供養塔として建立されていると云う。 豊臣家供養塔には一族の塔が並んでいて整然としていたが、織田信長の供養塔は単独であり、隣に武将筒井順慶の供養塔が並びチョット悲哀感が漂う。 |
 豊臣家供養塔入口 豊臣家供養塔入口 これが一番大きい! 秀吉供養塔 これが一番大きい! 秀吉供養塔 織田信長供養塔と筒井順慶供養塔 織田信長供養塔と筒井順慶供養塔 |
 秀吉、母公、淀君ら一族の供養塔 秀吉、母公、淀君ら一族の供養塔 無縁石仏がアチコチにある 無縁石仏がアチコチにある 御廟橋の右側に水向地蔵 御廟橋の右側に水向地蔵 |
|
御廟橋前に到着。 御廟橋の敷板石数は36枚あり、それぞれに金剛界曼荼羅1461尊の代表37尊の諸仏諸菩薩の象徴、種子が梵字で板裏に彫られている。 板数が一枚足らないのは橋全体を一つと見ているからだと云われている。 これに対して、胎蔵界は何処にあたるのかというと、大伽藍が胎蔵界だそうです。 |
 燈籠堂 燈籠堂 燈籠堂 燈籠堂 |
 御廟橋と燈籠堂 御廟橋と燈籠堂 |
|
燈籠堂は真然大徳が建立し、その後藤原道長によって治安3年(1023年)、現在の大きさの燈籠堂が建立された。
堂内正面には千年近く燃え続けていると伝わる二つの「消えずの火」がある。
一つは祈親上人が献じた祈親灯で、もう一つが白河上皇が献じた白河灯です。
この祈親灯を、貧しい生活の中、献灯したと伝わる貧女の一灯と呼び、一方、白河灯を長者の万灯と呼び、貧女の一灯、長者の万灯の伝説があるそうです。 |
 玉川の流水灌頂 玉川の流水灌頂 燈籠堂の横にある我が家本家の供養塔 燈籠堂の横にある我が家本家の供養塔 |
 流水灌頂 流水灌頂 我が家本家の供養塔 我が家本家の供養塔 |
|
燈籠堂、弘法大師御廟で読経を済ませると肩の力が抜けた感じでした。 再び御廟橋に戻り、緊張感がほぐれた瞬間です。 玉川の清流を背にして金仏の地藏菩薩や不動明王、観音菩薩が並んでいます。 奥の院に参詣するため、御供所で水向塔婆を求め、お地蔵さんに納め、水を手向け、先祖の冥福を祈る。 |
 水向地蔵 水向地蔵 奥の院御供所 奥の院御供所 |
 護摩堂 護摩堂 | | |
|
|
   |
||
 弘法大師御供所 弘法大師御供所 |
 弘法大師御供所 弘法大師御供所 |
|
☆彡 燈籠堂、護摩堂、頌徳殿、奥の院御供所、弘法大師御供所、我が家の供養塔 の拡大映像 ☆彡
|
 頌徳殿 頌徳殿 |
 | | |
|
高野山の供養塔群は、中の橋駐車場から入った広い公園のような供養塔がある場所で、明るく開放的な雰囲気で、企業の供養塔が多く並びます。 2つめは表参道。大名や戦国武将などの供養塔が建ち並び、石塔も大きく見ごたえがあり、 木立に囲まれ鬱蒼とした参道は時間をかけて歩きたい。 最後は聖域に近いエリアで、御供所などの宗教的な建物があり、また奥の橋から先は写真撮影禁止で、 数え切れないほどの灯篭で飾られた奥の院の大師廟は荘厳です。 |
||
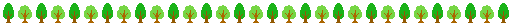 |