 
■ 紀伊山地高野山霊場と参詣道 ■ |
| ■…六時の鐘、常喜院から高野山大師教会へ…■ 壇上伽藍の蛇腹の小道を出ると金剛峯寺の六時の鐘があり、駐車場前に出る。 壇上伽藍のそばに高い石垣にある六時の鐘は、戦国武将福島正則が父母の追福菩提を祈って、1618年(元和4年)に建立された。 毎日午前6時より午後10時まで、偶数時に鐘を打ち時刻を知らせてくれる。 |
 六時の鐘の入口 六時の鐘の入口 |
 表から見た六時の鐘 表から見た六時の鐘 |
|
六時の鐘を見学し、高野山マップで次の見学コースを考え、高野山大師教会へ向かう。
途中、寺院に参拝しながらのんびり歩いてみます。
妻も歩き疲れてきたようで駐車場で休憩のタイミングを計らう。
|
 六時の鐘 六時の鐘 |
|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
■ 高野山真言宗 常喜院 ■ |
 常喜院正門 常喜院正門 常喜院のほとけのみ手 常喜院のほとけのみ手 |
 常喜院は平成の大修理中 常喜院は平成の大修理中 星形の石灯籠 星形の石灯籠 |
|
日本の仏像の中で、最も多いのがお地蔵さまで、お寺はもちろん、村のはずれや町かどなど、 さまざまな場所で見守っている。 お地蔵さまは庶民に身近に信仰されてきた仏さまで、功力は、六道の世界(地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天)にまで及び、 六地蔵としてお祀りされている。 本堂、大師堂で参拝し、隣の赤地蔵尊に向かう。 |
 本堂 本堂 |
 大師堂 大師堂 |
|
■ 常喜院赤地蔵尊 ■ |
 常喜院の赤地蔵尊、水かけ不動尊、聞耳地蔵尊 常喜院の赤地蔵尊、水かけ不動尊、聞耳地蔵尊 |
 | | |
|
常喜院の赤地蔵尊、水かけ不動尊、聞耳地蔵尊は全体が朱色で塗られ目立ちます。 二人で入ると、一願地蔵、水かけ不動尊、聞耳地蔵尊とあり、本尊に赤地蔵尊が祀られ、子供へのお地蔵さんがある。 二人でお賽銭とお参りしたが、妻は何をお参りしたのだろう。きっと孫たちへのお参りのよう。 |
  |
  |
|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
 高野山大師教会の白亜の門柱 高野山大師教会の白亜の門柱 |
 境内の右手にある石碑と石塔 境内の右手にある石碑と石塔 講堂 講堂 | | 弁財天融通橋 弁財天融通橋 | | |
 | | 本尊の弘法大師(境内から望遠で…) 本尊の弘法大師(境内から望遠で…) 弁財天のある蓮池 弁財天のある蓮池 蓮池の花が見頃で何枚か撮影 蓮池の花が見頃で何枚か撮影 大師教会総本部 大師教会総本部 |
|
駐車場そばの六時の鐘、常喜院、常喜院の赤地蔵尊、高野山大師教会と見学して、駐車場付近は金剛峯寺を残すだけになった。
半日の時間だが高野山の歴史がどういうものか勉強してきた。さらに知識を深めていきたい!
|
 |
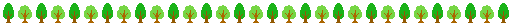 |